Giulietta Machine Discography
そっとそこにいてくれるだけで豊かな気持ちにさせてくれる。ジュリエッタ・マシーンの音楽は、手間のかかる仕込みをしていながら、そんなことを感じさせずに素材の味をしっかりと届けてくれる飽きのこない上質の料理のよう。 ----- 大友 良英
Discography
1st「Giulietta Machine」

「このレコードはなるべく大きな音で再生して下さい」とはロックのレコード・ジャケットにおける慣用句だけど、たまに「なるべく小さな音で再生して下さい」という言葉が似合いそうな風情の音楽にジャンルを問わず出会うことがある。ジョアン・ドナート、クララ・ハスキル、ウォーレン・G、アイレス・イン・ギャザ、ウォルト・ディッカーソン、ロバート・ワイアット、グラッドストン・アンダーソン、ラリー・ハード、ホーギー・カーマイケル、ハロルド・バッド…と挙げていくとキリが無いのだが、要はその静けさを感じさせる佇まい自体が、スピーカーから聴こえてくる旋律とは別のストーリーを物語る美しい音楽。
そして、このジュリエッタ・マシーンというユニットの処女アルバムもまた、「なるべく小さな音で再生して下さい」という言葉とともに人に薦めたくなるような、厳かな存在感を放つ作品だ。サンバ/ボサノヴァの精神性を匂わせながらも、限りなく室内楽に近いジャズであるような気もするし、サンプラーを用いたアヴァン・ポップと呼びたくもなる。
--ウィスパー・ヴォイス、ギターやピアノの抑制された音色、電子ノイズ、サンバや4ビートを刻みそうで刻まないリズム、カメラのシャッターのサンプリング音、特殊な音像定位。たとえばこういったフラグメンツが曖昧に結びつくことで聴く者の官能をひどく刺激する‘装置’として機能するのが、ジュリエッタ・マシーンの音楽だ。
女1と男2という映画的記憶を呼び覚ますメンバー構成もまた、このユニットの一つの味わい。E+o Naoko、02 Makoto、Fujii Novuoという3人のメンバーの経歴は別途プロフィールに目を通せばわかってしまうのだが、本作に接するときには一時忘れ、作品の中だけの三角関係を想像し楽しんでみてはどうだろう。それが「突然炎のごとく」なのか「淑女超特急」なのか「ファビュラス・ベイカー・ボーイズ」なのかはお任せする。ところでユニット名の由来を僕は知らない。「魂のジュリエッタ」でフェリーニの妻でもあるジュリエッタ・マシーナがやたら総天然色な白昼夢を見まくっていたことを思うと、プリンスの曲「エンドルフィン・マシーン」とほぼ同義で、つまりは聴くモルヒネということになるのか。いずれにせよ彼らの透き通ったサウンドは、致死量近い麻酔を含んでいるからこそ、艶やかさが漂っている。そして、その冷やかな感触は部屋の温度まで下げてくれそうだ。夏の昼下がりに何度も再生されることを推奨する。
(ライナーより:今村健一)
2nd 「Hula Pool
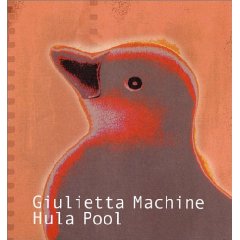
あらゆる音楽のエッセンスを随所にちりばめて、秘めた欲望を静かに刺激するひそやかな音楽。
初のボーカルトラック 2曲(6,8曲目)を加え、さらにアコースティック=エレクトロな音に磨きをかけた、
注目のセカンドアルバム。
その音楽は、何かの邪魔をすることなくそっと静かに漂い、じっと耳を澄まして鑑賞されることよりもむしろ積極的にBGMでありたいと密かに願っているかのような控えめな佇まいをみせながら、聴くものの耳に届く・・・。
(帯より)
3rd 「Cinema Giulietta」

数秒で虜、であった。
何だかわからないままに、サンプルをCDプレイヤーにかけてみて。
少なくとも、わたしにとっては、最高に趣味のいいサウンドだったのだ。こういう音楽を聴きたかった、と思った。
ひとの演奏する音楽でありつつ、どこかちょっと醒めていて、それでいながら、複数の音の、音楽の時間が併行しているので、聴き方によってそのときどきで、音楽のありようが変化する。
メロディ・ラインに耳をかたむけるのか、リズムに身体をのせているのか、ハーモニーの変化に瞬間に反応するのか。
この音楽には余計な厚みがない。暑み/熱み、とは誤用かもしれないが、そんなものはない。むしろ、うすさが魅力で、うすいからこそ、耳は、身体は、すっと音と音のあいだを行き来できる。
これを、さっきの「趣味の良さ」に置き換えてもそう遠くはないはずだ。
「趣味の良さ」なるものは、しばしば言われるわりにはわかったようでわからないような、でもわかったようなふりをしないといけないようなものである。趣味の良さとは、なんてわざわざ言おうものなら、それこそ趣味の良さがない奴、と認識されてしまうのがオチだから。でも、ほんとのところ、よくわかりはしない。何らかの文化的規範なるもの、一種のヒエラルキーがあるかのようだから、始末が悪い。趣味の良さを云々したいのだが、でもヒエラルキーの外にはいたい、それがホンネだし、そうありたいと思っている。そのうえで、むしろ古風な、反動的な、ヒエラルキーを肯定するような、趣味の良さ、をここではわざわざ言い立てたいのだ。だって、音楽がいいとかわるいとか、つまらない民主主義ではやっていけないでしょ?
Giulietta Machineは趣味がいい、とりあえずこう断言して、先に進もう。
「作曲」「アレンジ」「演奏」「録音」「ミックス」を分離せず、からみあうようなかたちで音楽をつくってゆく、という彼女/彼らは、 Giulietta Machineは言う。でも逆に、そうした生まれてくる音楽は、ときに、べつべつのところでべつべつのひとが音楽しているものが、偶然、何らかのかたちでひとつところで重なりあい、シンクロしているような不思議な感覚を味わわせてもくれる。そして、そこにある距離感、クールなかんじが、独特な魅力、先に記したような音楽のありようをつくっているようにも感じられる。さらには楽音や、非楽音、自然音、ノイズ、いまどこにでもひびく、ひびく可能性のあるさまざまな電子音、が、ごくふつうに共存する、してしまう。それがまさに、映画のなかのように、すべてが等価に扱われ、いまのわたし、わたしたちにはごくごく「自然」になっている、という事実。
Cinema Giulietta、今回はその名の由来どおり、ぐっと映画に接近である。
はじめにサンプルが届いたとき、仮のタイトルは「Soundtrack」となっていた。そうか、映画そのもの、映像はないけど、それは何らかのかたちで「サウンドトラック」なんだ、と思っていた。間もなく『Cinema Giulietta』に決まったと連絡がはいったが、なるほど、音の部分だけではなく、映画そのもの、映像も音も含めての運動性をあらわすシネマであるのに納得。そうなのだ、ずっと静止しているような映像であっても、かたかたとフィルムは動いているのと同様、音楽も、静かであるように感じられつつ、そこにはさまざまな音色の、リズムの、粒子がうごめいている。それを感じさせてくれるのがGiulietta Machineなのだ。
映画好きにとっては釈迦に説法だけれど、ジュリエッタ・マシーンというのは、イタリアの女優、ジュリエッタ・マシーナをもとにしている。名匠フェデリコ・フェリーニのつれあいで、『道』『魂のジュリエッタ』、そして齢を経てからの『ジンジャーとフレッド』といった作品に登場している。亡くなったのはフェリーニの没後5か月とのこと。
じゃあ、Giulietta Machineはこの女優とどうつながりがあるかといえば、よくわからない。女優マシーナは童顔でコケティッシュ、Giulietta Machineの江藤直子はといえば、スレンダーな美人で、わたしの見るかぎり、かなりキャラクターとしては隔たっているように思うのだが、まぁ、それはどうでもいい。大事なのは、往年の名女優の名、それもイタリア語であることと、Machinaがそのまま1文字変えれば機械に、マシーンに変わるという単純でありおもしろく、でも動かしがたい事実だろう。Giulietta/ジュリエッタは当然、シェークスピアのジュリエットを連想させ、つながり、そうした女性性と機械、マシーンが交差する、ふと重なってしまうところ、イメージにこそ意味がある。それがGiulietta Machineの音楽そのものともつながってきて、機械仕掛けの神ならぬ、機械仕掛けの女性、「未来のイヴ」を創始したのは19世紀フランスの作家、ヴィリエ・ドゥ・リラダンだったが、音楽の、ただテクノではない、かといってアコースティックでもない、その両方が創作プロセスにあって、システムそのものが女性の名を持っている、そんな「イメージ」----マトリックスとは、文字どおり、そういうものではなかったか?----が醸しだされているなら、それでいい、いいだろう。
これまでの2枚のアルバムと較べて、より「声」のはいってくる曲が多いのは偶然とは思えない。その声はときにセリフのようであり、語りのようでありつつ、でもうたにはならない、なりきらないながらも音楽として、音楽をなりたたせる部分であり、メロディになりそうでならない、なりきらない不安定さがまた耳を惹きつける。そうだ、アルバム『Cinema Giulietta』とは、音をさまざまなかたちで音楽のなかにとりこみつつ、映画を喚起するさまざまな要素を召還する誘惑の装置なのかもしれない。
このアルバムを聴いて、未知の----道の?----映画、ありえない映画を、音のみによる映画を想像するのか、それとも音・音楽でしかありえない映画を想像するのか。これらは、いずれにしろ、おなじこと、Giulietta Machineの幻惑であるにしろ。(小沼純一氏によるライナーノーツ)
4th 「Machina Nostalgia」

まったく具体性を伴わない「過去」が想起される。ここでの過去は、タイムマシンを使っても行き着くことのできない、理想的な過去。タイトルにある「ノスタルジア」は過去への憧憬であるが、では「マキーナ」はどうだろう。一般には「機械」であるが、ここはあえて「装置」と捉えたい。ファンタスマゴリーのような魔術としての装置。再生する度、美しい過去を現出させてくれる装置としてのアルバムが、この『マキーナ・ノスタルジア』ではないだろうか。アコースティックな音、電子音、様々な音楽ジャンルのエッセンス。これらをジュリエッタ・マシーンという坩堝に投げ込み、作り上げられた本作は、眼前に(あるいは脳内に)懐かしい理想郷を描き出すだろう。そして美しい過去への回帰願望は、究極の理想状態を目指していることに他ならない。
〜青野賢一
(BEAMS クリエイティブディレクター/BEAMS RECORDS ディレクター)〜
